貯蓄系の保険は本当に有利なのか?
学資保険や養老保険、その他「貯蓄系」と呼ばれる生命保険はたくさん存在しています。将来のために預金(銀行預金)よりも有利に運用できます。といった形で勧誘されたことがあるという人も多いのではないでしょうか?でもそれは本当に有利なのでしょうか?
貯蓄系の保険には落とし穴も多い。
学資保険や養老保険、終身保険といったように、保険に「貯蓄性」を売りにしたものも多数あります。生命保険における「死亡時の保障」ではなく、貯蓄を主眼と置いたものです。
こうした保険は、利回りベースにすると2%程度の銀行預金などと比較すると多少高く見える金利が付与されたものも多いです。
しかしながら、こうした貯蓄系の保険には大きな落とし穴があります。
1)契約期間が超長期
まずは、基本的にこうした貯蓄系の保険は契約期間が15年とか20年といった超長期です。それだけの長い間保険料を支払い続けることになります。
一方で比較対象となる預金などはおおよそ1年〜3年程度のものがほとんどです。
そうした比較はフェアではありません。(一般に運用期間(固定期間)が長い運用商品ほど利回りは高くなる)
2)固定利回りでインフレに対応できない
近年販売されている貯蓄系の保険のほとんどが「無配当型」です。
これは、将来保険会社が当初計画を上回る収益を出した場合であっても契約者には還元しないというタイプの保険です。
つまり、貯蓄性の保険の大半は「固定利回り」になるわけです。
超低金利と言われる現在において固定利回りで運用するのは、将来インフレになり、利回りをインフレ率が上回った場合には実質的に目減りすることになります。
3)途中解約リスク
貯蓄系の保険最大のリスクともいえるのが「途中解約リスク」です。
大抵の保険は満期前に解約をすると、受け取れる金額が小さくなります。契約期間にもよりますが、貯蓄系の保険であっても途中解約だとマイナス(元本割れ)になるケースも多いです。
途中解約時にどのくらい戻ってくるのかを示すものに「解約返戻率」というものがあります。
100%でこれまでに支払ってきた保険料と同額が戻ってくることになるわけです。
ちなみに、長期加入を前提とした貯蓄系の保険の代表ともいえる「個人年金保険」の解約・失効率は平成24年度において「3.7%」です。1年に加入者の3.7%が解約・失効していると考えた場合、20年継続できる確率は全体の50%を下回ることになります。
半数以上は途中で解約することになるわけです。
その場合は予定した利回りは約束されませんし、場合によっては元本割れとなる可能性も十分にあるわけです。
4)保険会社の倒産リスク
保険会社が倒産した場合には受けとれる保険金などは当初約束されたものよりも小さくなる可能性もあります。
まとめ。保険で貯蓄は決してメリットの高い運用方法ではない
「保険は原則的に損をする。期待値はマイナス」でも書いたとおり、保険は投資信託も真っ青の高い手数料を抜かれている金融商品です。そうした商品ではいかに上手に運用しようとも高い成果が見込めるわけではありません。
また、生保業界では過去に「約束していた利回りを反故にした経緯」もあります。
いわゆるバブル期に約束した利回りを維持できず、契約者側にそれを負担させたわけです。
それは保険会社の倒産を防ぎ、さらに多くの被害を出さないために必要不可欠であったとは考えますが、これもリスクとして考える必要があります。
それでも逆ざや状態は続いており、現在の契約者はその逆ざや分も負担しています。
言い換えれば、バブル期の保険契約者への高い利回りをねん出するために、現在の契約者へ約束する利回りを低くしてその分を充当しているような状態です。
貯金・貯蓄として運用するのであれば、自由度の高い「ネットバンクの定期預金」などで運用する方がよほど安全だと思います。
また、収益性を期待するのであれば株式投資のような投資のほうが手数料が安い分魅力的です。運用は面倒というのであれば投資信託のような形でプロに任せるという方法だってあります(投資信託も手数料は高いですが、保険に比べたら相当マシです)。
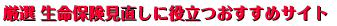
| 生命保険についての知識を自分で身につけ、それを使って賢く生命保険を見直すためのアドバイスサイトです。保険の基礎から、見直しの方法、そもそも保険が必要なのかなどを分かりやすく解説しています。 |
