保険の保障性と私たちの生活とリスク管理
保険はリスクの発生に伴う損失を皆で負担しあう相互扶助的なシステムです。こういった損失を皆でカバーするという保険の機能のことを「保険の保障性」と呼びます。ここでは、その保険の保障性についてより分かりやすく説明していきます。
リスクについて考えてみよう
まず、リスクについて考えていきましょう。
どちらが欲しいか考えてみてください。
設問1
(1):50%の確率で1億1000万円もらえる
(2):必ず5000万円をもらえる
回答は人によって異なると思いますが、おそらく多くの方は(2)を選択するとおもいます。
一方で次の場合はどうでしょうか?
設問2
(1):50%の確率で1100円もらえる
(2):必ず500円をもらえる
こちらの場合は(1)を選択される方も増えているはずです。
数学で言う期待値でいえば、(1)の方がメリットがあります。(1)の期待値は5500万円(550円)だからです。(2)の期待値は5000万円(500円)だからです。
経済合理的に考えるとどちらのケースでも(1)を選択するべきなのに、金額によっては非合理的なものを選択します。これは、人は金額が大きくなると「より確実なものを望む」という傾向があるからなのです。
保険というものも実は似たようなものです。
保険で備えるべきリスクの多くは、一個人では対処できない(できたとしても損害が大きい)ものです。死亡や事故、災害などによる被害は場合によっては人生を悪い方に大きく買えることもあります。
そうした大きなマイナスを予防するという保障性(補償)に生命保険や損害保険などの保険は役に立ちます。保険商品は「期待値ではマイナス」となる金融商品です。
しかしながら、 そのマイナスを考えたとしても、大きなリスクに備えるという意味で保険には確かな価値があるのです。
日本人はリスクに備え過ぎという考えも
その一方で日本人は保険に入り過ぎともいわれています。期待値では損をするわけですので、無駄な保険に入る必要はありません。
特に、医療保険などで入院補償などはどこまで必要なのか?預貯金では対応できないのか?と言ったことを考えるのも必要です。
もしも、入院に100万円が必要だとして、すでに貯金で数100万円を確保できているのであればわざわざ100万円を補償する保険に入る意味はないともいえます。
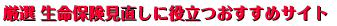
| 生命保険についての知識を自分で身につけ、それを使って賢く生命保険を見直すためのアドバイスサイトです。保険の基礎から、見直しの方法、そもそも保険が必要なのかなどを分かりやすく解説しています。 |
